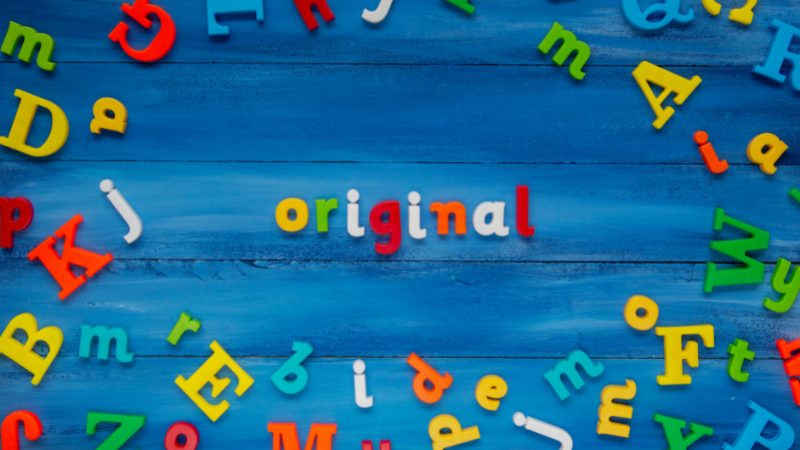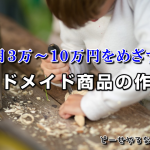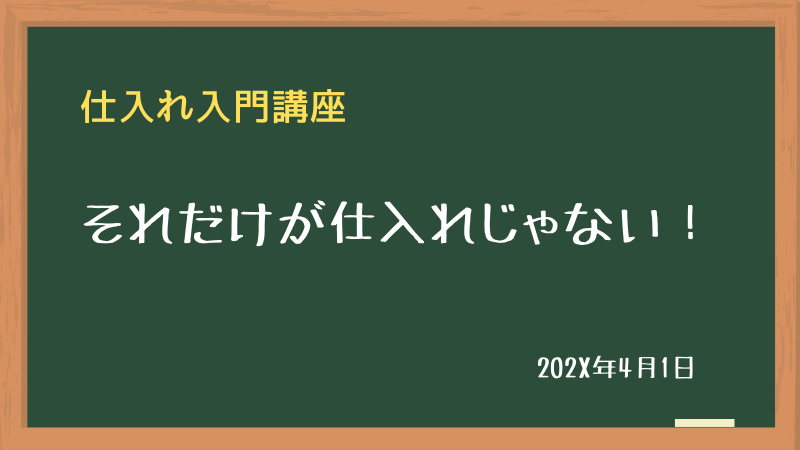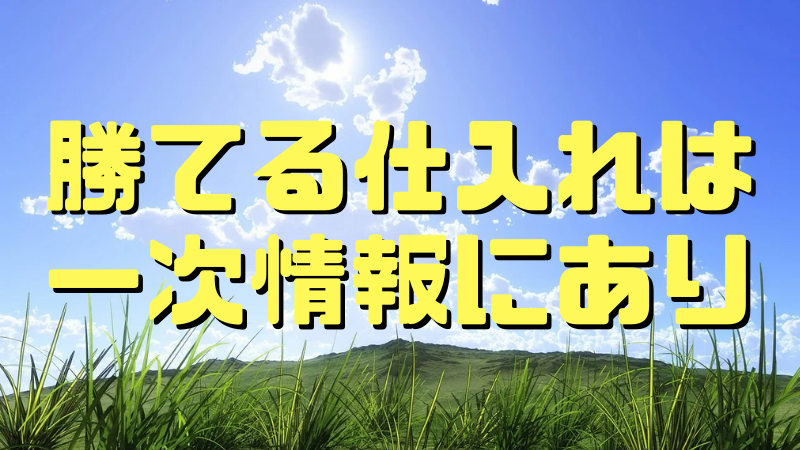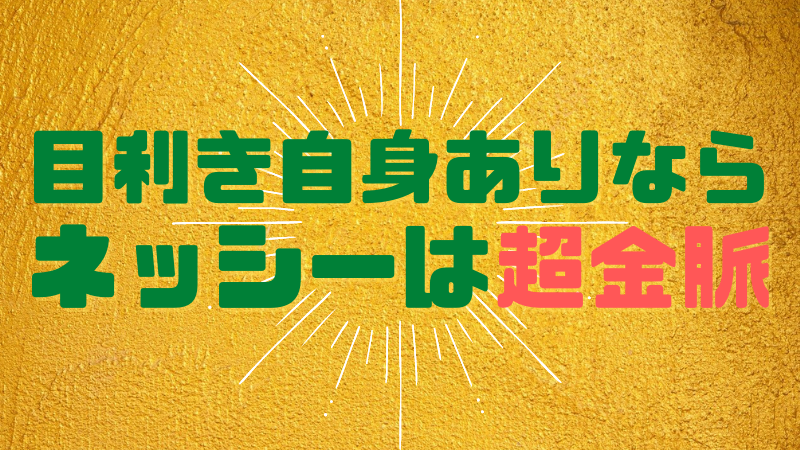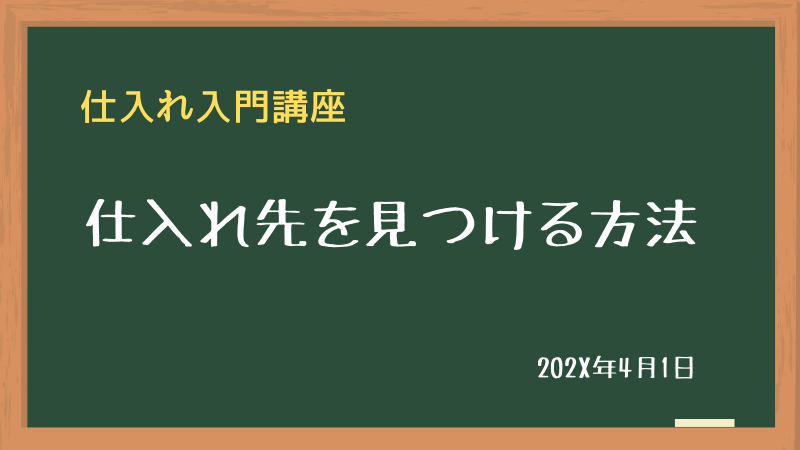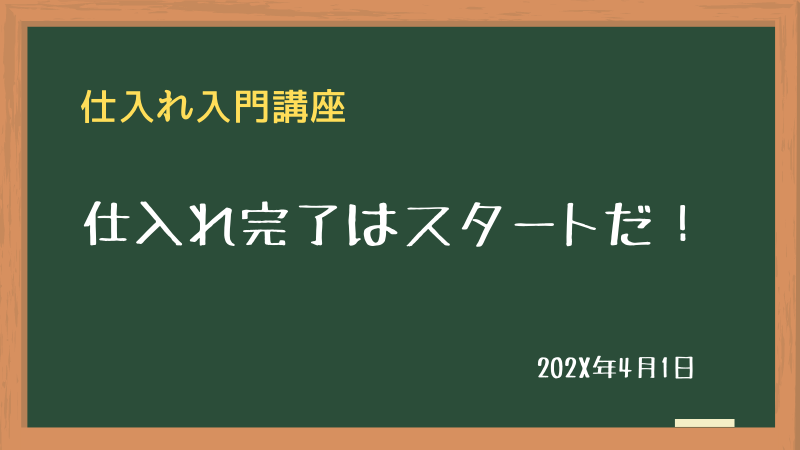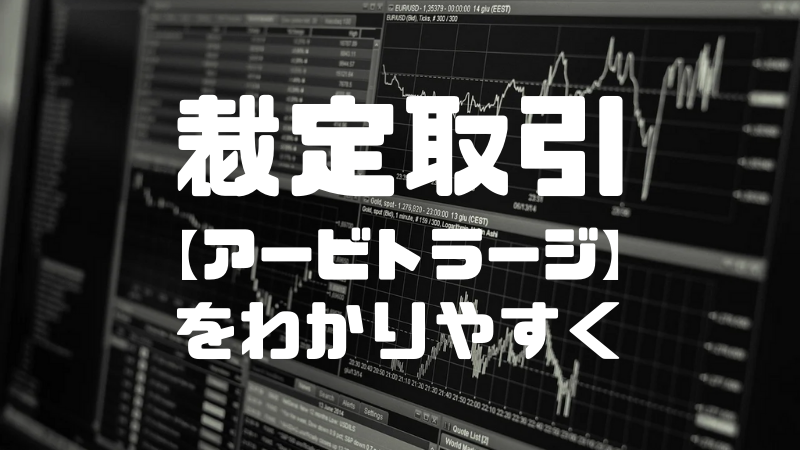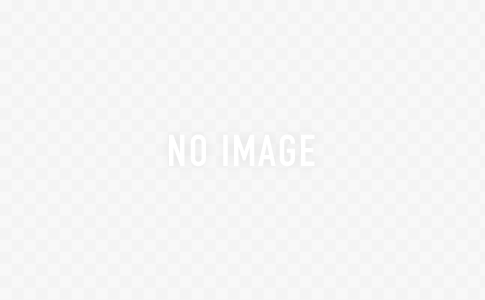主婦のハンドメイド手芸用品から家電製品まで。
個人だろうが法人だろうが、作ろうと思えばオリジナル商品を作ることができます。
もちろん、オリジナル商品を作るためには経験や知識、資金、あるいは、ときとしてネットワークも必要になります。
材料を安く簡単に調達できるものから、海外工場に頼らなければいけない大掛かりものまで様々です。
オリジナル商品の大メリット
オリジナル商品は、第一に夢があります。
全然売れないかもしれないし、もしかすると、大ヒットするかもしれない。
「新商品の9割は売れない。」とよく言われますが、逆をいうと1割は売れるということ。
ならば10回チャレンジすれば1個はあたるんじゃね?」と考えられます。
また、オリジナル商品は、販売価格は自由に決められます。
実質独占販売です。
だから、ライバルとの価格競争で苦しむこともなく、楽しく気持ちよく殿様的に販売ができます。
オリジナル製品は4パターン+変則パターン1
オリジナル商品は、だいたい4パターンに分けることができます。
ハンドメイド品
同じみの「ハンドメイド作品」。
手芸用品店などで材料を調達して、自分が職人・作家となってカバンや帽子、アクセサリーなどを製作するパータンです。
材料が国内で簡単に調達できて、すぐに生産できる反面、1つの商品を作るのに時間がかかり受けられる注文数に限界があるデメリットがあります。
アイデアとちょっとした技術だけでお金を生み出すことができます。
「松ぼっくりをメルカリで購入。それでクリスマス用のリースを作って販売。」そんなアイデアもあります(実際にやっている人いますね。)。
既製品にオリジナリティーをプラス
既製品に「オリジナルデザインをプラス」するタイプ。
Tシャツやパーカー、マグカップなど無地の既成品にオリジナルのプリントやデザインを載せることでオリジナル商品になります。
金型などから製作する費用がかからない反面、差別化できるのは視覚的なデザインだけになります。

「Tシャツトリニティー」や「ClubT」など、ネットのオンデマンドサービスを使うと、このようなオリジナルデザインのTシャツやトートバッグ、スマホケースなどが作れます。
海外製品を日本仕様に
海外製品を輸入し「日本版」として販売するパターン。
元のアイデアは海外で、オリジナルではありませんが、国内で販売しているのは「自社だけ」という点ではオリジナルです。
「メーカー」として販売するというよりは輸入商社として販売するイメージが強いです。
わかりやすい例で言うと「iPhone」。もともとは、アメリカAppleの製品ですが、日本のソフトバンクが売り出しました。もちろん、ソフトバンクのオリジナルではありませんが、当時は同社だけが販売していたという点ではオリジナルです。
この手の商品は、中国などで作られて「日本語化」して日本国内で流通している商品が非常に多いです。
開発は中国。それを日本に持ってきて売るパターンです。
パッケージを日本仕様にデザインしなおしたり説明書を翻訳したりる。
また、電源なども日本仕様に変更することもあります。
完全オリジナル商品
無から有を作るパターン。
完全オリジナル製品です。
企画からデザイン設計、試作、製造まですべて自社中心で行います。
例えば、財布やカバンを作る場合。
何十メートルという単位で革や合皮、あるいは、その他の生地を購入して、数百個単位、数千個単位など「大量ロット」で生産します。
完全な独自性を打ち出せる反面、時間や資金がかかり在庫のリスクも伴います 。
「何十メートルの生地を購入する」と言っても、自社内に在庫する場合もあれば、国内から指示を出して工場から工場へ手配する場合もあります。
例えば、「中国で生地を購入して、それをベトナムの工場へ送り製造、日本に輸入する。」といった感じです。
また、国内でも少量生産で作ることもあります。
国内の人件費は海外に比べ高いので、それないりにコストはかかりますが、品質は高く細かい指示も出しやすいし、品切れで入荷に数か月ということもありません。
転用することで一瞬でオリジナル
変則パターンです。
転用とは、簡単に言えば、本来の用途ではない別の用途のものとして売り出すということです。
例えば、本来大工さんが工具を入れるケースを、ステイショナリーの「ペンケース」として販売するようなパターン(東急ハンズなんかで見かけた人もいるかも?)。
「工具入れA」といった商品名がついていたとしても、それを「職人ペンケース」という風に商品名を変えて販売します。
元々、ボルダリングやフリークライミングで使われる「チョークバッグ」が、ファッションの1アイテムになったこともありました。
製品の製造は、中国やタイ、ベトナムなどの海外工場に依頼することが多いです。
アパレルなどでは、最近ポルトガルなども人気です。
コンテナ1本2本と、丸々輸入する本格的なやり方から、「混載(LCL)」と言ってコンテナの一部を借りて輸入する方法などがあります。
自社が海外工場と直接打ち合わせをしながら進めていくパターンから、個人で企画を出して、海外の工場のやりとりや輸入手続きなどは国内や海外の商社に代行してもらうパターンもあります。
小規模のメーカーの場合は後者のほうが多い印象です。
オリジナル商品を作る7ステップ
新商品の企画から製造、販売は、おおむね、次のようなステップで進めます。
大企業でも個人でも、だいたいこういった流れですすめるのが一般的です。
わかりやすく7ステップに分けてみました。
- 1.アイデアや妄想
- 2.販売戦略を練る
- 3.仕様書や設計図の作成
- 4.試作品の製作
- 5.試作品のテストと改善
- 6.製造開始
- 7.発売開始
ハンドメイドの場合、ここまで細かく分けてやることはないと思いますが、海外工場と提携して、金型から作って製造、輸入するようなケースでは、大きな費用とリスクがかかっているので、綿密な戦略や計画で進めていきます。
アイデアと妄想
「こんなモノ作ったら売れるかも?」ふとした思いつきがきっかけになったり、「これは確実に市場のニーズがある。」と確信して企画に入ったりパターンはいろいろです。
頭の中の話なので、いくらでも考えられますし基本タダですからね。
できるだけたくさんのアイデアや企画を出すのがポイントでしょう。(数撃ちゃあたる!)
そして、それらを一つ一つ、市場の状況なども合わせ論理的に「売れるのか」どうかを考えて突き詰めていきます。
販売戦略を練る
この段階も半分頭の中の作業です。
モノが完成したとして、いつ、どこで、どのように、誰に対して販売するのかなどを考えます。
市場の規模を考えて初回の生産数量なども考えます。
企画書などを作成することもあります。
すでにお店をやっている場合は、どういったお客さんに販売するのかターゲットを決めたり色やタイプ、数量などを決めたりします。
また、重要なことですが、商品をローンチ(発売)した後、他社がマネする可能性も考慮して、特殊な技術などがあれば特許や実用新案、意匠登録などを済ませます。
これらの申請はそれなりに費用がかかるのでペイできるかどうかも考慮しなければいけない点です。
当社の場合は、単価の安い商品ですし、パクられるのが当たり前の業界なので、よほどのことがない限りいちいち意匠登録や商標登録はしません。
いかに早く世に出して売り上げを取り込むか、といったスピード勝負です。
仕様書や設計図の作成
ある程度企画が決まればサンプル作成の準備です。
突拍子もないモノだと工場もどうやって作れば良いのかわからないため。
設計書や仕様書、洋服ならパターンなどが必要になりますが、ある程度既成品に類似したようなモノだと実績のある工場(例えば中国)なら、だいたいの仕様で作ってくれることもあります。
工場によりけり、ですが、手書きのイラスト的なものでも、対応してくれる場合がもります。
担当者とやり取りをしながら詳細を詰めて、試作を作ることもあります。
もちろん、サンプルを作るのにも費用がかかります。
試作品の製作や製造を専門にするメーカーもあるくらいです。
海外工場で作った場合は、通常は空輸するので、製品化では1万円の予定のモノでも、サンプルは30万円50万円とかかったりします。
ほとんどが空輸代ですね。国内の場合は輸送費がカットできるので、その分安くなります。
試作品の製作
試作品ができあがってチェックするわけですが、レベルの低い工場だとガッカリするものができあがりますが、レベルの高い工場だとイメージに近いものが仕上がってきます。
一発でイメージ通りのモノができれば良いのですが、通常は、何回か修正を加えながらイメージに近づけていきます。
ただ、試作を繰り返洗せば繰り返すほどコストがかさむので、最初のプロトタイプで設計段階で、いかに理想に近づけるかが勝負どころです。
設計段階ではあらゆるリスクも想定する必要があります。
ハンドメイドも同じですね。自分が工場ですから、設計図をもとに試作品を作り。改善を重ねます。
この段階は、とにかく頭を使うし時間もかかります。あせらず、じっくりやりたいところです。
ただし、試作から税品製造までの経験がないと、「作りたい」けど「作れない」といったギャップに足止めを食らうこともあると思います。
工場ならなんでも作れってわけではありません。「ここはR(カーブのこと)をつけて」と指示しても、「ごめんこの素材はRはできないんだわ。」なんてこともあるので、事前に細かくやり取りすることが大事ですね。
試作品のテストと改善
雑貨なら強度やデザインなど物理的なチェックだけで済みますが、電気を使うようなモノだと動作チェックや耐久テストなども必要になってきます。
場合によっては、検査機関に依頼してテストしてもらうこともあります。
製造開始
販売するための条件がクリアできたらいざ製造開始です。
1日でできれば良いのですが、工場もいろいろな製造案件を抱えていることが多いので数ヶ月はかかるのもよくあることです。
それにプラスして、船便で輸入する場合は更に数ヶ月要します。企画から販売開始までの期間が1年を超えることも珍しくありません。
なお、製造は1個から作ってくれると良いのですが既製品の仕入れと同じでメーカー工場ごとに最低ロット数があります。
「3000個から」あるいは「1アイテム100枚、5アイテムから」などです。
販売開始
完成品を販路に流します。一般的なメーカーの場合は小売店宛に新商品のインフォメーションを流し発注を促します。
ですが、通常は、完成する前に予告して顧客小売店から受注を取り、完成と同時に各店舗に発送する流れです。
完成してからお知らせでは遅すぎますからね。
これがネット販売の場合は、完成前からランディングページの企画から設計、制作を経て、発売日には「公開」、そして、メルマガや広告で告知、といった形になります。
100%確実に売れるオリジナル商品とは
ちょっと難しい話ですが、興味のある方はお付き合いを・・・
オリジナル商品を世の中に出すには、2つのやり方があるのをご存知でしょうか。
(A)「これ、絶対はウケるんじゃない?」と「開発者のアイデアが元」になって製造されるモノです。
2つ目は、(B)「どうやら、こういう商品を欲しがってる人が多いから、「それ作ろうよ。」と、欲しがっている人が多数いることがわかっていて製造するモノです。
前者(A)のことをプロダクトアウト。(B)のことをマーケットイン。と言います。
確実に売れるのはマーケットインです。プロダクトアウトは、企画者のアイデアと需要が合っていないと大失敗します。
世の中を見渡すと、このプロダクトアウトで失敗していった製品がたくさんあることに気づくと思います。
「あれ?そう言えば、あの商品見かけないなぁ~」なんて商品は、開発者のアイデア先行で、市場では、結局求められていなかったので製造中止になったりするわけです。
という話だと、「プロダクト・アウト」はダメじゃん。なんて話になりそうですが、世の中、そう単純じゃございません。
消費者のニーズなど考えず、ふとしたアイデアで製品を作ってみたところ「大ヒットしてしまった」なんて商品もたくさんあります。
開発者も「なんでそんなに売れるのか意味がわからない・・・」といったこともあります。
アジャイル開発で行こう!
アジャイル開発とは、簡単に言えば「完全じゃないけど売り出しちぇえ!」というノリの開発スタイルです。
そうすることで、アイデアをいち早く市場に出せます。
今の世の中変化が激しいので、完全になるまでじっくり時間をかけていては商機を逃してしまう恐れがあります。
もちろん、不完全なものをマーケットに出すとクレームだらけで売れなくなってしまいます。
でも、そのクレームやお客さんの声(フィードバック)をいち早くキャッチし、改善したバージョンをリリースします。
このようなやり方で成功しているのが、スマホの充電機などクロモノ家電メーカーのAnker(アンカー:Google出身者が立ち上げた中国シンセンに本部のある会社)です。
販売プラットフォームをアマゾンにして、レビューなど顧客の反応を見ながら、改善点が見つかったならすぐに工場に指示を出し、次のバッチ(製造単位)からマイナーチェンジを加える、といったことを繰り返してクオリティーの高い製品を作り続けています。
通常ネットショップもオリジナル商品を開発しよう
チョコレートに印刷してくれる業者があって、「これノベルティーにいいな!」って思って聞いたら、最小ロット5000個からって・・・
もうね、5000個とか1万個とか小規模なネットショップには無理。
どうせ在庫の山になること間違いなし。
だから、小規模なネットショップは小ロットがマストですね。
ま、ノベルティーは関係ないですが、当店で作っている小ロットオリジナル商品のやり方をちょこっとご紹介しましょう。
当店は、もともと「メーカーや商社から型番商品を仕入れてネット販売する。」というのがメイン事業でした。
今も、それが基本になっているのですが、楽天のクソ安売り店やアマゾンなどに客を奪われて、人気商品も落ち目という悩みがありました。
そこで、やはり強いのはオンリーワンのオリジナル商品。
工場に発注するような商品はどうしてもロットが5000、1万という数になってしまいます。
だから、狙うのは小ロットでオーダーメードで作っている企業を見つる方法。
当店では1個から作ってくれる企業しか狙いません。
というのも、在庫を持ちたくないから。
まず、アイデアがあれば、それをオーダーメードで作ります。
そして売ります。
初回は、あまり利益は乗せられませんが、1度作ると、設計図も残りますし納期も原価もわかります。
初回作った商品をネットショップに載せておき注文が入れば業者に発注するという、受注発注の方式です。
まあ、今のところバカ売れするようなものはありませんが、「年に1回1件注文が入って利益2万円。」といった商品ばかりです。
でもね、年に1回注文が入って利益2万円の商品を100個作れば、理論上年間200万円の利益がでるわけです。
当店では、まだ数点しかありませんが、今後、オリジナル商品は拡充していく方向です。
消費者は値段がわからない
実は、オーダーメードで作るものって、一般消費者にとって値段がわかりにくいってのがあります。
だから、オーダーメードでやっている企業は、たまにふっかけてくることがあります。
ちょっきんで作ったオリジナル商品は数社見積もりを取ったところ・・・
A社:20,000円
B社:55,000円(八丁堀の○○ドットコムはダメ)
C社:32,000円
と、かなりのばらつきがありました。
当然A社を利用するわけですが、やはり、オーダーメードでオリジナル商品を作る場合は3~5社は、しっかり相見積をとったほうが良いですね。
B社なんか、完全に消費者をバカにした値段を提示してきましたからね。
騙されないよう注意しましょう。
ちなみに、オーダーメードって言っても、TシャツトリニティーとかClub-Tとかオンデマンドで作るやつじゃないですよ。
図面を作って工場と直接やりとりをして作るやつです。
個人でやっているような人も多いです。
ココナラやクリーマとかでも、けっこう見つかります。